葬儀にまつわるコラム
七回忌とは?家族だけでするの?いろいろな疑問を徹底解消
2025.11.06
目次
七回忌は、故人様がご逝去されてから満6年目に執り行う年忌法要です。一周忌や三回忌よりも小規模で執り行うことが多く、ご遺族やご親族のみで供養するのが一般的です。 七回忌は、ご遺族にとって一つの節目となる大切な法要です。法要当日の流れやマナーを事前にしっかり確認し、安心して故人様を偲ぶことができるよう準備を進めましょう。今回は、七回忌について徹底解説します。七回忌の一般的な流れやマナーも紹介するので、ご参考にしてみてください。
七回忌は故人様がご逝去されてから満6年目に執り行う法要
七回忌とは、故人様がご逝去されてから満6年目にあたる祥月命日に執り行う年忌法要のことです。故人様がご逝去された年を「1年目」と数えるため、満6年目は「7年目」にあたり、「七回忌」と定められています。七回忌は、故人様の供養の節目となる大切な法要です。一周忌や三回忌は、ご遺族やご親族のみならず、故人様と関係性の深い方々を多く招き、比較的大きな規模で執り行われるのが一般的です。
一方、七回忌には、故人様の供養の一つの区切りという意味合いがあるため、参列するのは基本的にご遺族とご親族のみで、規模は比較的小さく執り行われる傾向があります。 七回忌以降も、「十三忌」や「十七忌」などの年忌法要がありますが、近年では省略するケースも増えています。七回忌は、故人様の供養の節目であり、ご遺族やご親族の心の区切りともいえる重要な年忌法要です。
七回忌の参列者は?家族だけでもいい?
結論から申し上げますと、七回忌の参列者はご遺族やご親族のみとし、ご家族だけで執り行っても問題ありません。七回忌では、一周忌や三回忌とは異なり、参列者の範囲を縮小することが多く、ご家族だけで穏やかに故人様を偲ぶという形式が一般化しています。しかし、これはあくまで一般的な傾向であり、厳密な決まりがあるわけではありません。
ご家族以外にも、故人様と関係性の深い方が参列されることもあります。七回忌の参列者を決める際に大切なのは、故人様の生前のご意向を尊重することです。ご遺族やご親族でよく話し合い、みなさまが納得できる形で執り行いましょう。
七回忌の一般的な流れ
七回忌では、僧侶による読経や会食などが執り行われます。七回忌の一般的な流れは、以下のとおりです。
- 喪主の開式挨拶
- 僧侶の読経
- 焼香
- 僧侶の法話
- 喪主の閉式挨拶
- 会食
- 返礼品の配布
喪主の開式挨拶では、故人様を偲ぶ想いと参列者への感謝が伝えられます。 開式後は僧侶が入場し、読経が行われます。焼香は喪主、ご遺族やご親族、一般の参列者、の順で進めるのが一般的です。読経と焼香の後は、僧侶による法話があります。喪主の閉式挨拶にて、七回忌の法要は終了です。法要後は、お斎(おとき)という会食を執り行います。お斎には僧侶も参加するのが一般的ですが、辞退される場合もあります。僧侶が会食を辞退される場合は、「御膳料」としてお布施とは別に金銭をお渡しするのがマナーです。
七回忌のマナー
七回忌では、略喪服(平服)を着用するのが一般的なマナーです。ご遺族は参列者にお渡しする返礼品を準備したり、参列者は持参する香典の金額相場を確認したりすることも大切です。 七回忌のマナーを解説します。
服装は略喪服(平服)を着用する
七回忌では、略喪服(平服)を着用するのが一般的です。 一周忌や三回忌まで着用した「正喪服」や「準喪服」は、着用しなくても構いません。 ただし、略喪服(平服)は、「普段着」という意味合いではない点に注意が必要です。 男性は紺色やグレーなどのダークスーツ、女性は黒色や紺色などのワンピースやアンサンブルを着用しましょう。 ご家族のみの法要であっても、弔事であることを意識し、派手な装いは避けるのがマナーです。
参列者には返礼品をお渡しする
七回忌にご遺族やご親族以外の一般の方が参列される場合は、返礼品を用意しましょう。 返礼品は、会食の有無にかかわらず準備します。 返礼品の金額の目安は、香典の金額の3分の1から半額程度です。お菓子やお茶、洗剤など、持ち運びやすく後に残らない「消えもの」を選ぶのが基本的なマナーです。返礼品の表書きは「志」とし、黒白の結び切りののしを使用しましょう。
香典の金額相場は3千円から5万円
七回忌の香典の金額相場は、故人様との関係性によって大きく異なります。 七回忌以降の法要では、一周忌や三回忌よりも香典の金額相場が低くなるのが一般的です。 一般的な七回忌の香典の金額相場は、以下のとおりです。
- ご家族(配偶者やお子様):1〜5万円程度
- ご親族(兄弟姉妹や孫など):1〜3万円程度
- ご親戚(従兄弟や叔父叔母など):5千円〜1万円程度
- ご友人・知人:3千円〜1万円程度
故人様と関係性が近くなるほど、包む香典の金額相場は高くなります。 参列者の年齢によっても適切な金額は異なるため、不安な場合はご親族間で話し合うことをおすすめします。 また、法要後の会食(お斎)に出席する場合は、会食の費用として5千円~1万円程度を上乗せして包むのがマナーです。小さな子どもが出席する場合は、大人の会食費用の半額程度を包みましょう。
返礼品を受け取る
お通夜の受付では、ご遺族からの感謝の印として、返礼品を渡されることがあります。 返礼品を受け取る際は、「恐れ入ります」といった言葉を添えて両手で丁寧に受け取り、軽く一礼しましょう。返礼品を受け取った後は、担当者から「式場へどうぞ」などと案内がありますので、改めて一礼して案内に従います。
七回忌はご家族やご親族で執り行う大切な法要(まとめ)
七回忌は、故人様がご逝去されてから満6年目に執り行う、供養の一つの大きな節目となる年忌法要です。 一周忌や三回忌とは異なり、ご遺族やご親族のみで規模を縮小して執り行うことが多く、ご家族だけで故人様を穏やかに偲ぶのが一般的です。 七回忌を滞りなく進めるためには、事前に日程や会場を決め、僧侶との連絡、会食やお斎の手配、返礼品の準備など、多くの準備が必要です。 ご遺族は参列者への服装の案内などを忘れないようにし、参列者は香典の金額相場など、マナーに関する配慮をしっかり行うようにしましょう。
ご遺族にとって七回忌は、故人様を偲ぶ大切な時間であり、心の区切りをつけるための重要な儀式です。 七回忌の準備や法要の流れに不安がある場合は、葬儀社や専門家にご相談することをおすすめします。お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区、都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。
[24時間年中無休]
お気軽にご連絡下さい。
 0120-310-866
0120-310-866
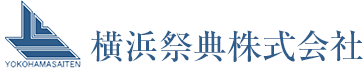
 0120-310-866
0120-310-866









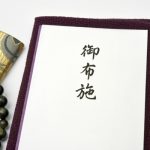

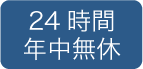
 0120-310-866
0120-310-866