葬儀にまつわるコラム
戒名一覧を徹底解説!宗派による戒名の違いとは
2025.09.09
目次
戒名とは、故人様が仏弟子(ぶつでし)になった証として与えられる名前のことです。 仏弟子は、お釈迦様の弟子や出家した弟子のことを意味します。 戒名は故人様に授けられる大切なお名前で、仏壇の位牌に記され供養されます。 戒名は菩薩寺の僧侶に授けてもらうのが一般的ですが、どのような付け方や位があるのか、気になりますよね。 今回は、戒名一覧について徹底解説します。 一般的な戒名の一覧、高位な戒名の一覧、宗派による戒名の違いを紹介するので、ご参考にしてみてください。
戒名とは
戒名とは、亡くなった方が仏様の弟子となり、極楽浄土へ行けるように授けられるお名前のことです。 戒名は、故人様が仏様の教えを守り、仏道に帰依したことを意味します。 生前のお名前である俗名とは別で、死後の世界で使われる大切なお名前として、仏壇のお位牌や墓石に刻まれます。 戒名は、菩提寺の僧侶に授けてもらうのが一般的です。 戒名には位があり、位の高さによってお布施の金額は変動します。 戒名は故人様の生前の人柄や寺院への貢献度、ご遺族の希望などを考慮して授けられます。
戒名は院号・道号・戒名・位号で構成される
戒名は、以下の4つで構成されています。
- 院号(いんごう)…戒名の一番上に付く尊称。戒名の中で最も位の高い部分。
- 道号(どうごう)…故人様の人柄や生前の功績などを表す称号。
- 戒名(かいみょう)…仏門に入った証として与えられる、最も中心となる部分。二文字で構成されるのが基本。
- 位号(いごう)…戒名の一番下に付く尊称。故人様の性別や年齢、社会的な地位などを表す部分。
院号(いんごう)は、社会や寺院に大きな貢献をした故人様に授けられます。 道号(どうごう)は、戒名の上に付けられる、故人様の人柄や生前の功績などを表す称号です。 戒名(かいみょう)は、基本的に生前のお名前から一文字と、仏様や経典から一文字をいただき、二文字で構成されます。 狭義での「戒名」は、ここの部分にあたります。 位号(いごう)は、戒名の一番下に付けられる、故人様の性別や年齢、社会的な地位などを表す称号です。 これらの組み合わせによって、故人様の戒名と位が決まります。 位が高くなるほど、授けられる文字数は増え、お布施も高額になります。
一般的な戒名の一覧
一般的な戒名には、「信士・信女」、「居士・大姉」があります。 さらに位が上がると、「院信士・院信女」、浄土真宗では「釋・釋尼」を授かることもあります。 一般的な戒名の一覧を紹介します。
信士・信女
信士(しんじ)は成人男性、信女(しんにょ)は成人女性に授けられる、最も一般的な戒名の位号です。 「仏教を信仰している人」を意味し、仏教に帰依したことが認められます。
居士・大姉
居士(こじ)は成人男性、大姉(だいし)は成人女性に授けられる位号です。 江戸時代は、上級武士などに使われており、庶民に授けられることはありませんでした。 そのため、信士・信女よりも一段上の位として、社会的に貢献した方や、信仰心が強い方に授けられます。
院信士・院信女
院信士(いんしんじ)は成人男性、院信女(いんしんにょ)は成人女性に授けられる位号です。 一般人に授けられる戒名としては、最も高い位の位号です。 社会的身分の高い方や、特別な貢献をした方に授けられます。
釋・釋尼
釋・釋尼は、浄土真宗で用いられています。 釋(しゃく)は成人男性、釋尼(しゃくに)は成人女性に授けられる位号です。 浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼ばれています。 浄土真宗における法名は、他の宗派の戒名とは異なり、すべての人に平等に与えられます。
高位な戒名の一覧
高位な戒名には、浄土真宗の「院釋・院釈尼」、日蓮宗の「院日信士・院日信女」があります。 位が上がると、「院居士・院大姉」を授かることもあります。 高位な戒名の一覧を紹介します。
院釋・院釈尼
院釋・院釈尼は、浄土真宗で用いられています。 院釋(いんしゃく)は成人男性、院釋尼(いんしゃくに)は成人女性に授けられる法名です。 浄土真宗では非常に高い位の法名であり、生前に寺院や社会に大きな貢献をした方に授けられます。
院日信士・院日信女
院日信士・院日信女は、日蓮宗で用いられています。 院日信士(いんにちしんじ)成人は男性、院日信女(いんにちしんにょ)は女性に授けられます。 日蓮宗では、高い位を表します。
院居士・院大姉
院居士(いんこじ)は成人男性、院大姉(いんだいし)は成人女性に授けられます。 院号と居士・大姉を組み合わせたもので、極めて高位な戒名です。 生前に寺院や社会に多大な功績を残した方や、信仰心が強い方に授けられます。
宗派による戒名の違い
戒名は、宗派によっても異なります。 故人様の宗派の慣習に応じて、適切な戒名を授けてもらうようにしましょう。 宗派による戒名の違いを解説します。
浄土真宗
浄土真宗では、戒名ではなく法名(ほうみょう)と呼びます。 法名は、「釋(しゃく)」または「釋尼(しゃくに)」の二文字で構成され、すべての人に平等に授けられるのが特徴です。 位号は基本的にありませんが、院号が付く場合もあります。
日蓮宗
日蓮宗では、戒名の位号に法号(ほうごう)が付きます。 男性は「法」の字が、女性は「妙」の字が入ることが多いのが特徴です。
天台宗・真言宗
天台宗や真言宗では、一般的な戒名の位号である「信士・信女」や「居士・大姉」が用いられます。 ただし、宗派独自の決まりや慣習によって、戒名に特定の文字を入れる場合があります。
曹洞宗・臨済宗
曹洞宗や臨済宗でも、一般的な戒名の位号が用いられます。 また、戒名の上に道号が付き、故人様の人柄や功績を表すのが特徴です。
戒名は故人様に授けられる大切なお名前(まとめ)
戒名は、故人様が仏様の弟子となった証として授けられる、とても大切なお名前です。 授けられる位は、故人様の生前の功績や信仰する宗派、包むお布施の金額などによって大きく異なります。 戒名は、故人様のお人柄や想いを尊重し、ふさわしいお名前を授けていただくことが大切です。 宗派による違いや、それぞれの位号が持つ意味を理解しておくことは、ご遺族が故人様への最後の供養として、納得のいく戒名を選択をするために不可欠です。 ご家族でよく話し合い、戒名を授かる過程を通じて、故人様と向き合う時間を大切にしてくださいね。
お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区、都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。
[24時間年中無休]
お気軽にご連絡下さい。
 0120-310-866
0120-310-866
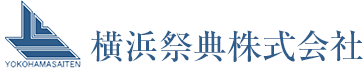
 0120-310-866
0120-310-866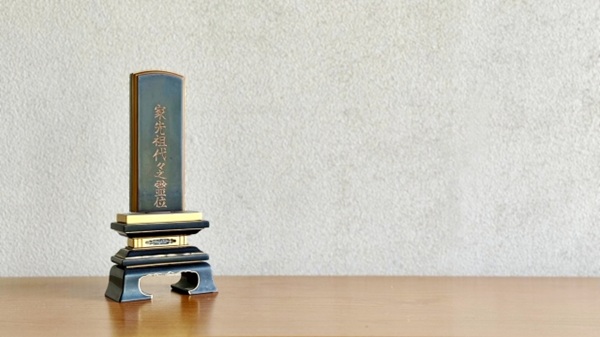







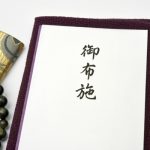

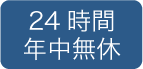
 0120-310-866
0120-310-866