葬儀にまつわるコラム
荼毘(だび)とは?火葬との違いは?「荼毘に付す」の意味も徹底解説
2025.04.07
荼毘(だび)は、火葬を意味する仏教・葬儀用語です。 故人様のご遺体を焼いて弔う意味合いがあります。 では、なぜ「火葬」ではなく「荼毘」という言葉を使うことがあるのでしょうか。「荼毘に付す」という表現をすることが多く見受けられますが、どういった意味があるのか気になる方もいらっしゃるかと思います。今回は、仏教・葬儀用語の「荼毘(だび)」について解説します。 「荼毘に付す」の意味と使い方と例文、類似語、荼毘式についても解説するので、ご参考にしてみてください。
荼毘(だび)とは
荼毘(だび)は、サンスクリット語で燃やす・火葬を意味する「dhyapayati(ディヤーパヤティ)」という言葉が語源となっています。 この言葉が日本に伝わった際、音写によって「荼毘」という漢字が当てられたことが由来です。荼毘は由来のとおり、火葬を意味します。 荼毘(火葬)は故人様の魂を浄化し、成仏させるための儀式として、重要な意味を持っています。
仏教における「燃やす」という行為と強く結びついており、死後の浄化や成仏、新たな生への移行を象徴するものとして大切に使われている言葉であり概念です。
荼毘と火葬の違い
荼毘と火葬の違いは、まず仏教用語であるかどうかにあります。 荼毘は仏教用語であるため、仏式の宗派において故人様を火葬することを表現する際に使われます。 ご遺族以外に対しては、「荼毘される」、「荼毘された」などと表現するのが一般的です。 一方、火葬は仏教用語ではないため、宗派を問わず使うことができます。
荼毘には仏教の教えや思想が紐づいていますが、火葬には宗教的な思想は含まれていません。 火葬は「死体を焼いて、残った骨を葬ること」という意味であり、公的な場でも使われています。 荼毘も火葬もご遺体を焼いて弔うことを意味しますが、前者は宗教的な側面が強く、後者は行為的な用語であるといえるでしょう。
「荼毘に付す」の意味と使い方と例文
実は、荼毘という言葉が単体で使われることは少なく、主に「荼毘に付す」という表現します。 「荼毘に付す」は、火葬を意味する「荼毘」と決定や措置を意味する「付す」が合わさった言葉です。 つまり、「火葬をする(した)」という意味になります。 火葬を執り行うことを、より丁寧に表す表現として使われる言葉でもあります。荼毘に付すの例文は、以下のとおりです。
故人様のご遺体は、荼毘に付される前に僧侶による読経がおこなわれた 彼は長年の闘病生活を経て、ついに荼毘に付された 伝説によれば、その英雄は戦いの後、戦場で荼毘に付されたという 動物園で飼育されていた象が死んだ後、荼毘に付されることとなった 事件の後、証拠となる物品はすべて証拠品として荼毘に付された 例文にあるように、荼毘は人に対してだけでなく、動物やペットなどを火葬する際にも使われます。また、比喩的に「何かを終わらせる」や「処分する」という意味で使われることもあります。
荼毘の類似語
荼毘の類似語には、「火葬」、「遺体焼却」、「灰にする」などがあります。 「荼毘」との違いは「火葬」との違いと同じく、宗教的な意味合いや思想が深く紐づいているかどうかにあります。「遺体焼却」も「灰にする」も、直接的に火葬や燃やすことを表現している言葉であり、故人様とご遺族に弔意を示す際には、マナーとして使わないほうがいい言葉です。
荼毘式について
荼毘式とは、火葬する直前に執り行われる法要儀式、または火葬だけを執り行う儀式のことです。法要儀式としての荼毘式を執り行う場合は、お通夜や葬儀・告別式などを省略するのが一般的です。荼毘式は家族葬と混合されがちですが、家族葬は家族だけで執り行う小規模な葬儀であって、お通夜や葬儀などを省略しません。
法要儀式としての荼毘式の一般的な流れは、以下のとおりです。 故人様のご臨終後、ご遺体を自宅や安置所に安置する(法律上ご逝去されてから24時間以内は火葬ができないため) 納棺と出棺をおこなう 火葬炉の前で僧侶に読経をしてもらう ※省略されることもあります 約1〜2時間かけて火葬が執り行われる 火葬後にご遺骨を骨壷へと納める「骨上げ」が執り行われる 荼毘式は、故人様の成仏を願う大切な儀式です。僧侶による読経をおこなうかどうかは、ご遺族のご意向や地域の慣習などによって異なります。
荼毘式の費用相場は、約15〜20万円です。 僧侶に読経してもらう場合は、お布施が必要となります。 ただし、荼毘式(火葬)にかかる費用は、公営か民営かによって大きく変わります。 公営の場合は数千円~5万円、民営の場合は5~15万円程度が目安です。 一般葬や家族葬と比較すると大きく費用を抑えられるため、最低限の法要儀式に留めたい場合や、ご遺族が高齢であったり少なかったりする場合に選ばれることが多いようです。
荼毘は火葬を意味する仏教用語(まとめ)
荼毘は、火葬を意味する仏教用語であり、火葬の丁寧な表現としても使われています。 火葬との違いは、仏教用語であり宗教的な思想が含まれていることです。 火葬は宗派を問わず使われる言葉ですが、荼毘は仏教でしか使われません。また、荼毘は基本的に「荼毘に付す」という表現で使われています。
荼毘に付すは「火葬をする(した)」という意味をもち、火葬を執り行うことをより丁寧に表す際にも採用されています。 荼毘は火葬を意味する仏教用語ですが、荼毘式といって荼毘に付す前に簡易的な法要儀式を執り行うこともあります。 荼毘式は火葬炉の前で執り行われる小規模な儀式ですが、僧侶を呼んで読経してもらうこともできます。
お通夜や葬儀などを執り行う意向がなく、火葬だけをシンプルに執り行いたいけれど、最後のお別れの時間として簡易的な法要儀式を執り行いたい…という方に選ばれています。 荼毘は故人様の魂の浄化と成仏を祈り、神聖な儀式として火葬を執り行うことを表現できる、素敵な仏教用語です。お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区、都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。
[24時間年中無休]
お気軽にご連絡下さい。
 0120-310-866
0120-310-866
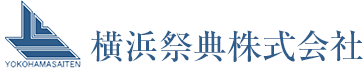
 0120-310-866
0120-310-866








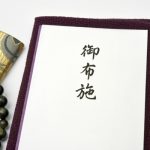

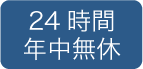
 0120-310-866
0120-310-866