葬儀にまつわるコラム
【現代版】喪中にやってはいけないこと・やってもいいこと
2025.05.15
目次
喪中にはやってはいけないことが存在しますが、現代の価値観においては、昔と少し考え方が変わってきているようです。 現代では、喪中にやってはいけないことの範囲が狭まってきている傾向にあります。 とはいえ、昔ながらの習わしは現代においても尊重されており、喪中は故人様を偲び供養する大切な期間として、配慮しながら慎ましやかに過ごすことが大切です。
今回は、現代の価値観を考慮したうえで、喪中にやってはいけないこと・やっても問題ないとされていることを解説します。 喪中期間の過ごし方を考えるうえで大切なことも解説するので、ご参考にしてください。
喪中にやってはいけないことがあるのはなぜ?
日本では喪中期間に特定の行動を慎む習わしが、古くから今日まで大切にされてきました。 根底にあるのは、故人様がお亡くなりになった後の一定期間を、残されたご遺族が故人様を深く悼み、供養に専念するための大切な、「喪に服す」期間と捉える伝統的な考え方です。喪中期間は慶事の主催や参列、引っ越しや宴会など派手な行動を控えることで、故人様への哀悼の意を示し、静かに故人様を偲びます。
喪中期間は、ご遺族が自身の心身を落ち着かせ、故人様との別れを受け入れるための大切な時間でもあります。 時代の変化によって、喪中期間の過ごし方は少しずつ変容していますが、現代においても故人様への敬意と感謝の気持ちを持って慎ましく過ごす、という大切な意味合いは変わりません。
喪中にやってはいけないこととは
喪中にやってはいけないことには、結婚式の主催や新年の挨拶や正月飾りがあります。喪中期間は神社への参拝や公の場での派手な行動や宴会も、控えたほうがよいでしょう。 現代における喪中にやってはいけないことについて解説します。
結婚式の主催
結婚式は、お祝い事の中でも特に華やかな慶事です。喪中期間は、結婚式のような慶事を主催することは、避けるべきとされています。 ただし、喪中期間に入る前に既に結婚式の日取りが決まっており、延期が難しいなど特別な事情がある場合は、予定通り敢行するケースが増えてきています。両家の話し合いや状況に応じて、慎重に判断しましょう。
新年の挨拶や正月飾り
お正月は、無事に新年を迎えられたことをお祝いする慶事です。喪中期間は故人様を偲ぶ期間であるため、「あけましておめでとうございます」といった新年の挨拶や、正月飾りでのお祝いは控えるようにしましょう。 年賀状も送付せず、友人や知人、会社関係者には「喪中はがき」にて、年賀の挨拶を欠礼することを事前に伝えておくのがマナーです。
神社への参拝
神社への参拝は、神聖な場所である神社に穢れを持ち込まないために、控えたほうがいいとされています。日本の古い考え方では、「死」は穢れと捉えていたことに起因しています。ただし、現代では個人の信仰や考え方、地域の慣習によって、解釈が異なる場合があります。故人様や神様への配慮として、神社への参拝は控えるのが基本的な考え方ですが、宗派や地域性によっては問題ないこともあります。
公の場での派手な行動や宴会
喪中は、故人様を偲び、慎ましく静かに過ごす期間です。 公の場での派手な行動や大勢が集まる賑やかな宴会への参加などは、なるべく控えるようにしましょう。喪中期間は派手な装いや言動を避け、静かに落ち着いて過ごすことが、故人様への哀悼と供養になります。ただし、仕事上の付き合いや避けられない会合などもあるため、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
喪中にやっても問題ないとされていること
現代において喪中にやっても問題ないとされていることは、親族や親しい友人の結婚式への参列です。七五三など身内の慶事への参加や故人様を偲ぶための旅行なども、基本的には問題ないとされています。現代における喪中にやっても問題ないとされていることについて解説します。
親族や親しい友人の結婚式への参列
伝統的には、喪中の慶事への参加は避けるべきといわれてきました。 しかし、現代では親族や親しい友人の結婚式であれば、参列しても問題ないとされることが増えています。故人様も慶事を祝っているだろうという考え方や、招待をしてくれた相手との関係性を重んじる配慮に起因しています。ただし、親族や親しい友人の結婚式に参列するときは、喪中期間であることを考慮し、派手な装いや振る舞いは控えるなど、配慮することが大切です。
七五三など身内の慶事への参加
七五三など身内でおこなわれる個人的なお祝い事については、喪中期間にやっても問題ないという風潮になってきています。 身内の入学・卒業や誕生日のお祝いなども同義です。故人様も家族の一員として、共に喜びたかったであろうという考え方に起因しています。ただし、大人数での派手な宴会などは避け、身内だけで故人様を偲びながら慎ましくお祝いするなど、配慮を欠かさないようにしましょう。
故人様を偲ぶための旅行
伝統的には、娯楽レジャーである旅行を喪中期間におこなうのは不適切だといわれてきました。しかし、現代では故人様との思い出の場所を巡る旅や故郷への帰省など、故人様を偲び心の整理をつけることを目的とした旅行であれば、問題ないとされることが多くなっています。
故人様と一緒に行く予定だった旅行も、予定通り敢行することが多いようです。 ただし、観光目的の派手な海外旅行などは、現在においても喪中期間は慎むべきという考え方もあります。 旅行に行く場合は、喪中期間であることを意識した過ごし方をすることが大切です。
喪中期間の過ごし方を考えるうえで大切なこと
喪中期間の過ごし方を考えるうえで大切なことは、故人様を偲び供養する気持ちを第一にすることです。喪中期間の過ごし方に、絶対的な決まりやマナー、タブーはありません。だからこそ、喪中期間の振る舞いや過ごし方は、故人様への想いが反映されるものであるべきではないでしょうか。
伝統的な考え方や一般的なマナーに従うことは大切ですが、故人様の生前のご意向やご意思に思いを巡らせるのも一つの供養の形です。古くからの習わしや宗派・地域の慣習を尊重しながらも、ご家族の状況や周囲への配慮を総合的に考えて、無理のない範囲で過ごし方を決めることが大切です。
喪中期間は故人様を偲び慎ましやかに過ごすことが大切(まとめ)
喪中期間は、故人様を偲び、供養に専念するための大切な時間です。 過ごし方に絶対的な決まりはありませんが、古くからの伝統と現代の価値観を考慮することが大切です。 一般的に、結婚式の主催や新年の挨拶、正月飾り、賑やかな宴会などは控えるべきとされています。
一方で、親しい関係者の慶事への参列や、故人を偲ぶ目的の旅行などは、現代では問題ないとされる傾向にあります。 どのような場合でも、故人様への哀悼の気持ちを第一に、ご家族の状況や周囲への配慮を忘れず、無理のない範囲で過ごし方を選択することが重要です。
お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区、都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。
[24時間年中無休]
お気軽にご連絡下さい。
 0120-310-866
0120-310-866
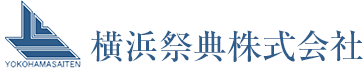
 0120-310-866
0120-310-866







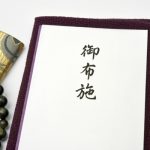

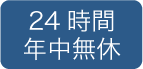
 0120-310-866
0120-310-866