葬儀にまつわるコラム
お布施でダメな金額は?一般的な金額相場や基本的なマナーも解説
2025.08.08
目次
お布施は、故人様の供養のために僧侶にお渡しする大切なものです。 しかし、お布施には明確な金額が定まっていません。 避けたほうがいい金額はあるのか、どれくらい包めばいいのか、お布施に関する疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。今回は、お布施で避けたほうがいい金額について解説します。お布施の一般的な金額相場や基本的なマナーも解説するので、ご参考にしてみてください。
お布施で避けたほうがいい金額
結論から申し上げますと、お布施で避けたほうがいい金額というのはありません。しかし、相場や戒名のランクにそぐわない金額は、失礼にあたることがあります。 人によっては、端数のある金額や縁起の悪い数字の金額を避けたほうがいいと考える方もいます。 お布施で避けたほうがいい金額について解説します。
相場や戒名の位にそぐわない金額
お布施の金額は、葬儀や法要の規模や読経の内容、授与される戒名の位(ランク)によって、ある程度の相場が存在します。 相場とかけ離れた、極端に高額または低額なお布施の金額は、避けた方が良いでしょう。お布施が高額すぎると、僧侶に過剰な気を遣わせてしまう可能性があります。ご遺族の負担も大きくなるため、特別な事情がない限りは、相場とかけ離れないよう留意しましょう。
反対に、お布施が低額すぎると、僧侶や寺院に対して失礼にあたる場合があります。相場を著しく下回る金額となることがないよう、配慮しましょう。故人様の供養のために僧侶や寺院にお渡しするお布施の金額に関しては、地域の慣習や葬儀における相場を事前に確認することが重要です。相場とかけ離れない範囲で無理せず、ご自身の気持ちに見合った金額を包むようにします。 お布施は「感謝の気持ち」を示すものであるため、金額が全てではありません。しかし、故人様への供養のためにも、僧侶や寺院には敬意を示し、失礼のないようマナーを守りましょう。
端数のある金額
お布施には、僧侶へ感謝の気持ちを示すだけでなく、寺院の活動を支えるという意味合いもあります。 金額に明確な決まりはありませんが、「〇万5,000円」や「〇万7,000円」といった端数の金額は避けるのが一般的なマナーです。端数の金額を避ける理由は、中途半端な印象を与えてしまい、失礼にあたる可能性があるからです。 端数は「切り上げ」や「切り捨て」を連想させてしまうため、不作法でもあります。お布施を包むときは、「3万円」や「5万円」といった、きりの良い金額にしましょう。
縁起の悪い数字の金額
慶事や弔事では、縁起の悪い数字を避けるのがマナーです。 縁起の悪い数字とは、「4」や「9」など「死」や「苦」を連想させるようなものです。 お布施でも、4万円や9万円など、縁起の悪い数字は避けるようにしましょう。また、慶事では「2」や「8」など割り切れる偶数を避ける慣習がありますが、弔事では基本的に問題ありません。ただし、人によっては不作法と捉えられる方もいらっしゃるため、気になる方は奇数の金額を包むようにしましょう。
お布施の一般的な金額相場
お布施の金額に明確な決まりはありませんが、一般的な金額相場を知っておくことは大切です。 お布施の一般的な金額相場は、以下のとおりです。
- 葬儀・告別式:約30〜50万円
- 四十九日法要: 約3〜5万円
- 納骨の儀: 約1〜3万円
- 初盆:約3〜5万円
- 一周忌や三回忌などの年忌法要: 約1〜5万円
葬儀・告別式のお布施の相場が高額な理由は、戒名の授与に対するお礼が含まれているからです。 戒名の位が高くなると、お布施の金額も高くなる傾向にあります。 上記の相場は、あくまで目安の金額です。実際には、葬儀の種類や規模、僧侶との関係性、寺院の格式などによって、金額相場は変動することがあります。地域や宗派の慣習などによっても変動するため、あくまでも参考としてお考えください。 お布施の金額を決めるときに最も大切なのは、感謝の気持ちを伝えることです。相場からかけ離れないよう配慮する必要はありますが、無理のない範囲でお渡ししましょう。
お布施の基本的なマナー
お布施には、金額以外にもマナーがあります。包み方、書き方、渡し方、それぞれに気を配りましょう。 お布施の基本的なマナーを解説します。
包み方
お布施は、白無地の封筒または半紙に包んでお渡しするのが基本的なマナーです。表に「御布施」「お布施」と印刷された、市販の専用封筒を用いることもできます。 ただし、柄や模様のある封筒は避けるようにしましょう。不幸を繰り返さないという意味合いから、「重ねる」という意味を持つ二重封筒も避けるのが作法です。
書き方
お布施の封筒の表書きには、「お布施」または「御布施」と書きます。筆記用具は、黒い筆ペンや毛筆を使用するのがマナーです。 お通夜の香典では悲しみを表現するために薄墨の筆記用具を使用しますが、お布施は感謝の気持ちを伝えるためのものであるため、黒墨を使います。中袋には、表面に「金〇萬圓也」と金額を旧字体で記し、裏面には住所と氏名を記入しましょう。 地域や宗派によっては慣習が異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
渡し方
お布施は、切手盆と呼ばれる小さなお盆の上に乗せてお渡しするのがマナーです。お盆が用意できない場合は、袱紗に包んだままお渡しするか、袱紗から取り出して袱紗の上に載せてお渡ししても問題ありません。お布施をお渡しするときは、「本日は、よろしくお願いいたします。どうぞお納めください」などと丁寧な言葉を添えるようにしましょう。葬儀後にお渡しする場合は、「本日は、ありがとうございました」などと、感謝の気持ちを伝えることも大切です。
お布施のマナーを知って安心して故人様を供養しましょう(まとめ)
お布施は、故人様を供養し僧侶に感謝の気持ちを表すもので、金額に明確な決まりはありません。しかし、相場からかけ離れた極端な金額は避け、戒名の位や地域の慣習、一般的なマナーに配慮することが大切です。端数のある金額や、「4万円」、「9万円」といった縁起の悪い数字は、不作法と受け取られる可能性があるため、避けるようにしましょう。
お布施には、金額以外にも基本的なマナーがあります。白無地の一重の封筒または半紙に包み、表書きは「お布施」と黒墨の筆ペンや毛筆で書くのが基本です。 中袋には、表面に旧字体で金額を書き、裏面に氏名と住所を記入します。お布施をお渡しするときは、直接手渡しするのではなく、切手盆や袱紗の上に載せて、丁寧な言葉を添えるようにしましょう。お布施に関するマナーは、故人様への供養と僧侶への敬意を示すための心遣いです。 不安な点がある場合は事前に葬儀社や寺院に相談し、安心して故人様をお見送りしましょう。
お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区、都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。
[24時間年中無休]
お気軽にご連絡下さい。
 0120-310-866
0120-310-866
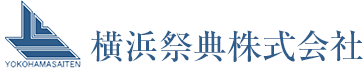
 0120-310-866
0120-310-866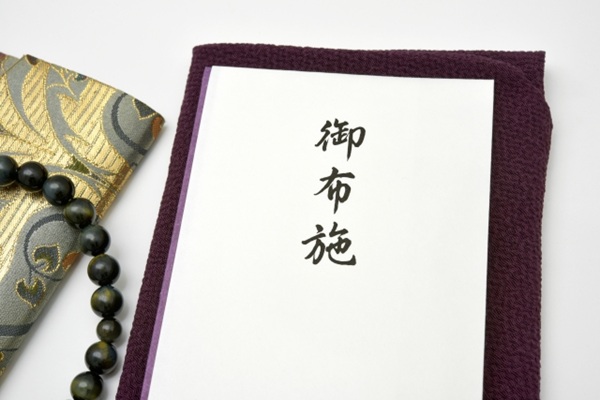








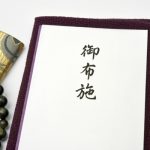

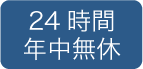
 0120-310-866
0120-310-866